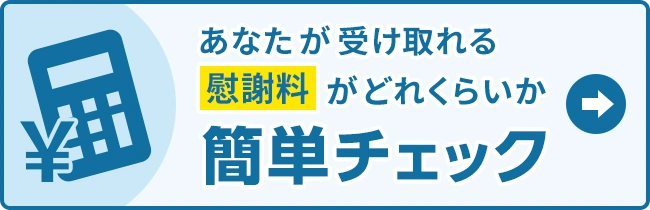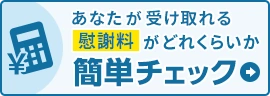- 目次
目・耳・鼻・口の後遺障害とは
1.交通事故による目の後遺障害
交通事故による目(眼)の後遺障害は、(1)視力に関する障害、(2)目の調整機能に関する障害、(3)眼球の運動機能に関する障害、(4)視野に関する障害、(5)まぶたの欠損に関する障害、(6)まぶたの運動に関する障害の6つに分類されます。そして、それぞれの障害の態様や程度によって、後遺障害の等級が定められています。
(1)視力に関する障害
交通事故によって視神経を損傷したり、眼球そのものに外傷を負ってしまうことによって、失明や視力の低下といった症状が生じることがあります。この場合、失明の有無や低下した視力の程度に応じて後遺障害の等級が認められることになります。失明や視力低下の場合による後遺障害の等級の認定基準は、下記のように定められています。
| 眼の機能障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第1級1号 | 両眼が失明したもの |
|---|---|
| 第2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 第3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| 第8級1号 | 1眼が失明し、又は1目の視力が0.02以下になったもの |
| 第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 第9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
| 第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
i 失明
失明とは眼球を失った場合や、明暗が判断できない、または明暗がようやく区別できる程度の場合のものとされています。
ii 視力の低下

視力は、万国式試視力表によって判断します。万国式試視力表とは「ランドルト環(アルファベットのCの形のようなもので、切れ目の方向を答えさせるもの)」やアラビア数字を用いて作られたものです。後遺障害等級表の視力は、矯正された視力をさし、メガネやコンタクトレンズ、眼内レンズなどを使用して得られた視力を意味します。つまり、原則的に、メガネやコンタクトレンズを使っても、なお視力の低下が認められる場合に、はじめて後遺障害として認定されることになるのです。
iii 視力低下の原因となる障害の検査
交通事故により視力が低下してしまう原因として、眼球の外傷や視神経の損傷があります。眼球の外傷については、スリット検査、直像鏡によって検査を行います。
スリット検査とは、細隙灯(さいげきとう)顕微鏡という装置を使って眼球を観察する検査方法です。細隙灯というスリットランプから細い光を眼球に照らし、眼球を顕微鏡で拡大して、結膜、角膜、前房、虹彩、瞳孔、水晶体、硝子体などの眼の各組織を直接観察して、異常がないかを検査します。直像鏡検査とは、直像鏡という装置を使い眼底部を直接観察して、眼底部の異常を発見する検査方法です。
これらの検査によっても異常が発見できない場合には、電気整理学的検査である網膜電図(ERG)などの検査が考えられます。人は目に光が入ると網膜にある光受容器細胞が刺激を受け、脳へ電気信号が送られます。網膜電図は、この網膜の光に対する反応を記録し、異常を発見する検査方法です。
次に、視神経損傷により視力が低下していると考えられる場合には、視覚誘発電位検査(VEP)という検査により、網膜から後頭葉に至る視覚伝達路の異常をチェックします。視覚誘発電位検査は、視覚的な刺激を外部から与え、これにより誘発される電位(脳波)を測定し、その異常を確認する検査方法です。人の脳は、目に映る光など外部の刺激に反応して、視覚誘発電位という形で表しており、これを検査することにより異常の有無を確認することができます。後遺障害の認定にあたっては、これらの検査による異常所見が認められることが有力な資料となります。
iv 頸椎捻挫(むち打ち)による視力の低下
頸椎捻挫が原因で視力低下の症状が現れる場合があります。頸椎捻挫により頚部交感神経に異常が生じ、視力が低下することがあると医学的にも認められています。しかし、交通事故により頸椎捻挫の障害を負ったとしても、視力の低下との因果関係を立証することは非常に難しく、頸椎捻挫を原因として視力低下の後遺障害は認められることはないといっても過言でありません。その場合、頸椎捻挫による神経障害として第12級、第14級などの後遺障害の獲得を目指すことになります。
(2)目の調整機能に関する障害
人の眼には、見たい距離に応じてピントを合わせる調整機能が備わっており、水晶体がその調整機能を担当します。この調整機能が失われたり、低下してしまうと、ピントが合わずに物がぼやけて見えるようになります。交通事故により水晶体を摘出せざるを得なくなったり、傷ついてしまったため調整機能が低下した場合には、後遺障害として認められる余地があります。具体的には、下記の等級が定められています。
なお、眼の調整力は、眼調節機能測定装置(アコモドポリレコーダー)を使って測りますが、眼の調節機能は加齢によっても失われますので、55歳以上の方の場合、調整力を失っていたとしても、後遺障害として認定されないケースが多いです。
| 眼の調節機能に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの ⇒具体的には 両眼の調節機能が正常な場合と比較して、2分の1以下になってしまった状態のことをいいます。 |
|---|---|
| 第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの ⇒具体的には 1眼の調節機能が正常な場合と比較して、2分の1以下になってしまった状態のことをいいます。 |
(3)眼球の運動機能に関する障害
人の眼球は、水平、垂直、回旋という3つの運動を行うことができ、これにより正常な視野が確保されます。しかし、交通事故により眼球運動を支配する神経を損傷したり、眼球の向きを変える筋肉である外眼筋が損傷されることにより、眼球の運動が制限されて視野が狭くなるなどの障害が生じることがあります。眼球の運動機能の後遺障害については、次のように定められています。
| 眼球の運動機能に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
|---|---|
| 第11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
| 第12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
| 第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
i 複視
眼球は、その周りを囲んでいる複数の眼筋によって正常な状態にバランス良く保たれています。その内のひとつの筋肉でも麻痺してしまうと、眼を支えるバランスが崩れ、眼の動きが制限されてしまうことによって、物が二重に見える症状が起こることがあります。これが、「複視」です。
複視の有無は、ヘススクリーンテストなどの眼球運動検査を行って測定します。ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法です。一般の眼科医では扱っていない場合もありますので、視神経を専門とする神経眼科などで検査してもらう必要があります。
「正面を見た場合に複視の症状を残すもの(第10級2号)」の場合は、ヘススクリーンテストにより正面を見た場合に複視が中心の位置にあることが確認される場合をいいます。逆に、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの(第13級2号)」とは、それ以外の複視の場合をいいます。
そして、具体的に「複視を残すもの」として認められるためには、(ア)本人が複視のあることを自覚していること、(イ)眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、(ウ)ヘススクリーンテストにより患側の像が健側の像よりも水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、が必要であるとされています。
ii 注視野の制限
このほか、眼球運動が制限されたことにより、注視野の広さが狭まった場合も、後遺障害が認定されることになります。注視野とは、頭部を固定した状態で眼球だけを動かして直視できる範囲のことをさします。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、注視野の広さが正常の場合の2分の1以下に狭まったものをいいます。上記の表にあるように、両眼の注視野が2分の1以下に狭まった場合は第11級1号、片眼だけの注視野が2分の1に狭まった場合は第12級1号が認定されることになります。
(4)視野に関する障害
目の前の1点を見つめたときに同時に見える外界の広さを「視野」といいます。眼で見た情報は、網膜から後頭葉の視中枢を通じて脳に伝えられますが、その伝達経路に何らかの損傷を受けると視野が狭くなるといった症状が現れることがあります。人の脳が実際に見える映像は、左右の眼によって感知した情報を脳内で合体させたものであり、左右の眼からの情報が何らかの障害により制限されると視野が狭まることになります。視野に関する後遺障害については、次のように定められています。
| 視野に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|---|---|
| 第13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
i 半盲症
『労災保険後遺障害診断書作成手引』によれば、「視神経繊維が、視野経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するもの」とされています。簡単にいうと、両眼がそれぞれ右半分ないし左半分しか見えないというレベルまで視野が狭まっている状態をいいます。
ii 視野狭窄
人の目に見える一定の範囲(視野)が狭まってしまうことをいいます。視野狭窄には、「求心性狭窄」と「不規則狭窄」とがあります。
求心性狭窄の場合、視野の周辺部分から中心に向かって視野が狭まっていき、不規則狭窄の場合は、文字通り不規則に視野が狭まる状態をいいます。視野の検査方法としては、視野を測定する視野計(ゴールドマン視野計)という器具を使います。人の正常の視野には個人差がありますが、日本人の平均値としては、耳側に約95度、鼻側に約60度、上側に約60度、下側に約70度見えている状態が正常であり、これらの値と比べて60%以下しか見えない状態であれば、視野狭窄と判断されることになります。
iii 視野変状
半盲症や視野狭窄のほか、視野欠損や暗点が生じて視野の一部に見えない部分が発生することをいいます。この場合の「暗点」とは、強い光でも感知することができない絶対暗点をさし、強い光以外は感知することができない比較暗点は含まれません。
(5)まぶたの欠損に関する障害
交通事故により、まぶたの全部または一部が欠損した場合や、まつ毛がはげてしまった場合には、下記の表にしたがって後遺障害が認定されることになります。まぶたの欠損については、外貌醜状としても捉えることができるので、外貌醜状による後遺障害の等級と比較として、より上位の等級が認められることになります。
| まぶたの欠損に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|---|---|
| 第11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 第13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
| 第14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたの欠損により角膜を完全に覆えない状態をいいます。また、「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたの一部により角膜を覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出してしまう状態をいいます。「まつげはげ」とは、まぶたの周囲に生えているまつ毛の2分の1以上がはげてしまった状態をいいます。
(6)まぶたの運動に関する障害
人のまぶたの運動には、まぶたを閉じる、開ける、瞬きするといった運動(調節機能)が備わっています。しかし、交通事故によるまぶたの神経麻痺や外傷などにより、そのような運動ができない、もしくは制限されてしまった場合には後遺障害が認められることになります。まぶたの運動障害については、下記の表にしたがって後遺障害が認定されることになります。
| まぶたの運動に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
|---|---|
| 第12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない状態である場合や、まぶたを開いたときでも、まぶたが完全に瞳孔を覆ってしまう状態などをさします。
2.交通事故による耳の後遺障害
交通事故により耳殻を失ってしまったり、聴力障害が生じたり、耳鳴り、耳漏などが残ってしまう場合など、耳に後遺障害が残ってしまうことがあります。また、耳の三半規管や耳石は平衡感覚を司っているため、平衡機能障害が生じることもあります。
(1)耳殻の欠損
耳殻は耳介とも呼ばれ、外見的に「耳」といわれる部分をさします。貝殻状の形は、音を集めるための働きをしているといわれています。この耳殻の部分を欠損した場合は、後遺障害が認定される余地があります。
後遺障害として認定されるのは、1耳の耳殻の大部分を欠損した場合であり、「大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合をいいます。この場合には第12級4号に該当することになります。両耳とも、「大部分の欠損」にあたる場合には、併合により第11級の後遺障害が認定されることになります。
また、耳殻の欠損は、外貌醜状の後遺障害ともとらえることができ、外貌醜状の後遺障害として認定される余地があります。外貌醜状の後遺障害は第7級~第12級があり、耳殻の欠損と比べてより高い等級が認定されることになります。なお、外貌醜状の場合は、耳殻の2分の1に達しない欠損でも外貌醜状に該当する余地があり、また、両耳の耳殻の欠損があっても併合にはあたらず、総合して外貌醜状の有無が判断されることになります。
| 耳殻の欠損に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⇒具体的には 1耳の耳殻の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合をいいます |
|---|---|
(2)聴力に関する障害
交通事故によって聴力が喪失したり、低下してしまった場合、後遺障害の認定対象となります。聴力検査にはさまざまなものがありますが、主に「純音聴力検査」と「語音聴力検査」で判定をします。
i 純音聴力検査
純音聴力検査は、一般的にオージオメータという検査機器を用いて検査するもので、音が聞こえるかどうかを検査するものです。人の聴力には、空気の振動によって音を把握する聴力である気導聴力と、頭蓋骨の振動によって音を把握する聴力である骨導聴力があり、この両方を検査することで純音聴力レベルを把握することができます。純音聴力検査の結果は、聴力レベルとデシベル(dB)という単位で表され、認定は3回以上の検査の平均で判断されます。
ii 語音聴力検査
語音聴力検査は、「に」「さん」「よん」「ご」など言葉の聞き取りやすさを調べる検査です。語音聴力検査の結果は明瞭度で表され、最高明瞭度を100%として、%という単位で表されます。
後遺障害の等級認定に必要な聴力の検査は、治療効果が期待できない状況、つまり症状が固定した後に行います。実施に際しては、日を変えて3回行い、検査と検査との間隔は少なくとも7日程度は空けなければなりません(ただし、語音聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回でもかまいません)。
耳鼻科医であっても、後遺障害認定のための検査方法を熟知しているとは限りませんので、検査にあたっては後遺障害認定のために必要であることを伝え、上記の点に踏まえて検査が行われているかを確認してください。
純音聴力検査や語音聴力検査は、被験者の返答を必要とする検査であるのに対し、そのような被験者の返答を必要としない検査として、ABRやSRという検査があります。ABRは、音の刺激に対する脳の電気生理学的な反応を感知して、その波形を記録する検査であり、SRは中耳のあぶみ骨にある耳小骨筋が音に反応して収縮することから、これを感知して検査する方法です。これらの検査は、他覚所見を確認するために純音聴力検査や語音聴力検査に加えて行われます。
聴力に関する後遺障害は、両耳と片耳の聴力に関して、その聴力低下の程度に応じて各等級が定められています。
| 両耳の聴力に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの ⇒具体的には 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、または両耳の平均純音聴力レベル80dB以上で、かつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。 |
|---|---|
| 第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB~80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。 |
| 第6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいいます。 |
| 第7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のものをいいます。 |
| 第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。 |
| 第9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 両耳の平均純音聴力レベルが両耳60dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のものをいいます。 |
| 第9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの ⇒具体的には 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上で、かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものをいいます。 |
| 第10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの ⇒具体的には 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のものをいいます。 |
| 第11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものをいいます。 |
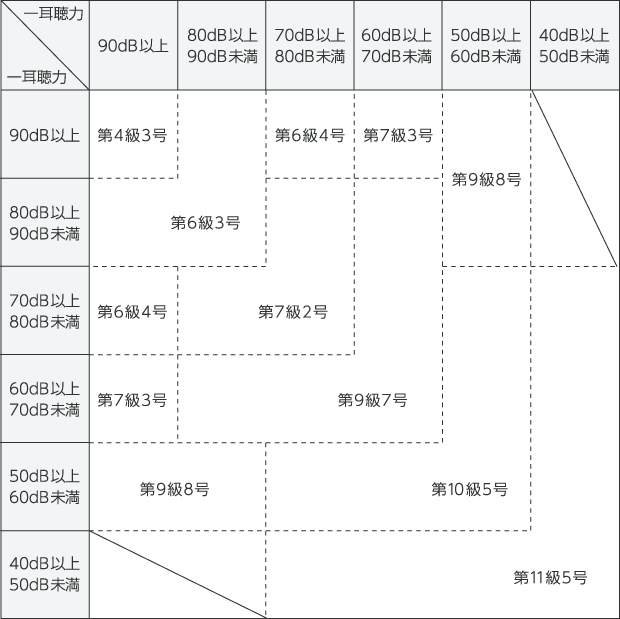
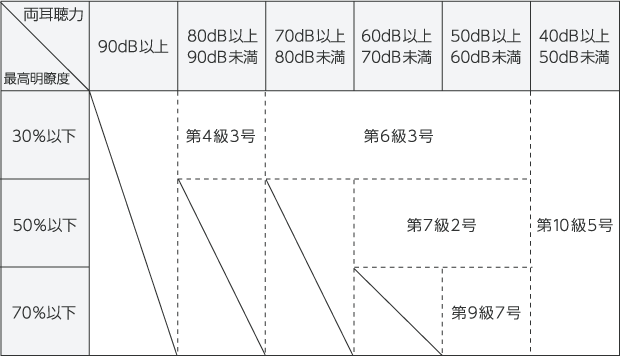
| 耳の聴力に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの ⇒具体的には 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものをいいます。 |
|---|---|
| 第10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 平均純音聴力レベルが80dB~90dB未満のものをいいます。 |
| 第11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 平均純音聴力レベルが70dB~80dB未満、または50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のものをいいます。 |
| 第14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⇒具体的には 平均純音聴力レベルが40dB~70dB未満のものをいいます。 |
(3)耳鳴りや耳漏
i 耳鳴り
交通事故の被害に遭った後に、耳鳴りが止まないなどの症状が残った場合は、後遺障害として認定される余地があります。耳鳴りの検査としては、「ピッチ・マッチ検査」や「ラウドネス・バランス検査」などの方法があります。
ピッチ・マッチ検査は、異なる23種類の音を聞き、耳鳴りがどの音に一番近いかを調べて「耳鳴りの周波数」を検査するものです。ラウドネス・バランス検査は、ピッチ・マッチ検査で特定された耳鳴りの周波数を使って、その周波数の音量を徐々に上げ下げしながら、耳鳴りと同じ大きさの音量を探り、「耳鳴りの音の大きさ」を検査するものです。ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査の両方を行うことで、どの高さの耳鳴りがどの程度の大きさで聞こえているのかを測定できることになります。
そして、耳鳴りが後遺障害として認定されるためには、30dB以上の難聴を伴うことが必要とされていますので、併せて聴力の検査(純音聴力検査や語音聴力検査など)を行う必要があります。耳鳴りの後遺障害の認定は労災の認定基準を準用しますが、耳鳴りの程度によって下記の表のように判断します。
| 耳鳴りに関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第12級相当 | 30dB以上の難聴をともない、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの |
|---|---|
| 第14級相当 | 30dB以上の難聴をともない、常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの |
「著しい耳鳴り」とは、上述の検査などで耳鳴りが存在することが認められていることを医学的に評価できる場合をいい、「常時」とは、昼間は自覚症状がなくても夜間に自覚症状が生じる場合も「常時」にあたるとされています。
ii 耳漏
耳漏とは、交通事故により鼓膜に穴が空いて分泌液が流れ出てしまう症状のことをいいます。耳漏が後遺障害と認定されるためには、手術により治療をしたうえでなお耳漏がある場合に加え、30dB以上の難聴を伴うことが必要とされています。労災の認定基準を準するのは耳鳴りの場合と同じです。
第12級相当30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
| 耳漏に関する障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第14級相当 | 30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの |
|---|---|
3.交通事故による鼻の後遺障害
交通事故による鼻の後遺障害としては、鼻の欠損、嗅覚脱失、嗅覚減退、鼻呼吸が困難になったなどがあります。
(1)鼻の欠損をともなう鼻の機能障害
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残した場合、後遺障害の第9級5号が認定されることになります。そして、鼻を「欠損」するとは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合を指します。
鼻の欠損にあたる場合はもちろんですが、大部分の欠損にあたらない場合でも、鼻の一部が欠損していることが外貌醜状にあたる場合には、外貌醜状による後遺障害として認定される余地があります。
外貌醜状は第7級~第12級までの幅がありますので、鼻の欠損による後遺障害第9級と比べて、より上位の等級が認められる場合は外貌醜状が認定されることになります。なお、両者の等級が併合されることはありません。より上位の等級の後遺障害だけが認められることになります。また、顔面への外貌醜状が鼻の欠損以外もある場合、たとえば、瘢痕などがある場合には、その瘢痕と鼻の欠損を併せて顔全体の外貌醜状を判断することになります。そのため、別々に外貌醜状の有無が判断されるわけではありませんので注意してください。
(2)鼻の欠損を伴わない鼻の機能障害
自賠責の後遺障害等級表には、鼻の欠損を伴う鼻の機能の著しい障害を残す場合のみが定められています。しかし、鼻の欠損を伴わない場合でも、その障害の程度に応じて、後遺障害の等級が認定されることになります。
嗅覚を失う(嗅覚脱失)、または鼻呼吸が困難な場合は第12級に相当するとされ、嗅覚が減退した場合(嗅覚減退)は第14級に相当するとされています。嗅覚の機能については、T&Tオルファクトメータという基準嗅力検査により判断されます。嗅覚脱失の場合は、平均嗅力損失値の認知域値が5.6以上、嗅覚減退の場合には、平均嗅力損失値の認知域値が2.6~5.5となります。
一般の耳鼻科では、T&Tオルファクトメータによる検査に対応していない場合もありますので、確認したうえで、対応している病院の紹介を受けるなどしてください。
| 鼻の機能障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第12級相当 | 嗅覚脱失または鼻呼吸困難 ⇒具体的には 嗅覚脱失の場合は、T&Tオルファクトメータによる平均嗅力喪失値の認知域値が5.6以上 |
|---|---|
| 第14級相当 | 嗅覚減退 ⇒具体的には T&Tオルファクトメータによる平均嗅力喪失値の認知域値が2.6~5.5 |
4.交通事故による口の後遺障害
口の後遺障害には、(1)咀嚼(噛み砕くこと)や言語の機能に障害が残る場合、(2)味覚に障害が残る場合、(3)歯牙の障害の3つがあります。それぞれの場合について、障害の程度に応じて後遺障害の等級が定められています。
(1)咀嚼や言語の機能障害
咀嚼(そしゃく)とは、食べたものを噛み砕き、消化を助けることをいいます。言語の機能とは、4種類の語音を発声する機能をいいます。交通事故によるこれらの機能障害については、その障害の程度に応じて下記のような後遺障害等級が定められています。
| 咀嚼や言語の機能障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの ⇒具体的には 流動食以外は食べられない状態、および4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合をいいます。 |
|---|---|
| 第3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの ⇒具体的には 流動食以外は食べられない状態、または4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合をいいます。 |
| 第4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ⇒具体的には
の両方を満たす場合をいいます。 |
| 第6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ⇒具体的には
のどちらかを満たす場合をいいます。 |
| 第9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ⇒具体的には
の両方を満たす場合をいいます。 |
| 第10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ⇒具体的には
のどちらかを満たす場合をいいます。 |
※4種類の語音
言語機能の後遺障害は、言語の音にあたる4種類の語音が発声できるかどうかによって区別されます。また、人の言語は、語音を一定の順序に連結して言語がつくられますが、これを「綴音(てつおん/ていおん)」といいます。
口唇音(こうしんおん)
…ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音(しぜつおん)
…な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口蓋音(こうがいおん)
…か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音(こうとうおん)
…は行音
(2)味覚の障害
交通事故によって頭部外傷やその他、舌や顎の組織が損傷してしまうことにより、味覚が失われる(味覚脱失)、味覚が減退する(味覚減退)などの機能障害が残ってしまうことがあります。
味覚の障害については、自賠責施行令に定める後遺障害等級表には明示されていませんが、同程度の後遺障害に準じて下記のように扱われます。味覚検査は、濾紙ディスク法における最高濃度溶液で味を認知できるかどうかで判定します
| 味覚の障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第12級相当 | 味覚を脱失したもの ⇒具体的には 甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本の味のすべてがわからない場合をいいます。 |
|---|---|
| 第14級相当 | 味覚を減退したもの ⇒具体的には 甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本の味のうち、ひとつ以上の味がわからない場合をいいます。 |
(3)歯牙の障害
口の後遺障害には歯を失った場合に認められる歯牙の障害があります。これは失った歯の本数に応じて後遺障害の等級が定まることになります。等級表にある「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯に対する補綴をいいます。
また、後遺障害等級の認定は「現実に喪失または著しく欠損した歯」の数を基準にされるため、差し歯や入れ歯(デンチャー)などで補綴されなかった場合も等級認定の対象になります。
喪失した歯の数と、義歯の数が一致しない場合には、喪失した歯の数を基準に補綴数を数えることになります。たとえば、4本の歯を喪失し、歯と歯の間に隙間があったため、5本の義歯を補綴した場合には、4歯の補綴として扱われることになるのです。
| 歯牙の障害 | |
| 該当する等級(自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |
| 第10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|---|---|
| 第11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |