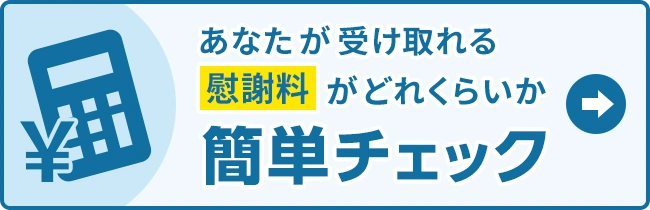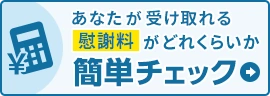- 目次
車両自体に生じた損害
1.修理費
交通事故で車両が破損した場合、被害者は、原則として修理費相当額を損害として請求することができます。
もっとも、修理費全額が必ず損害として認められるわけではなく、修理が必要でまた修理費が相当と認められる場合に限られます。したがって、板金修理で足りるところをあえてパネル交換した場合や、部分塗装で足りるところをあえて全塗装した場合等には、板金修理費用や部分塗装費用を超える修理費は損害として認められませんし、修理自体が相当でも修理費用が不当に高額である場合には、相当額を超える修理費は損害として認められません。
ちなみに、車両が物理的に修理不可能な程度に損壊している場合(物理的全損)、修理費が事故車両の交通事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合(経済的全損)、または車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、その買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合には、修理費ではなく、次で述べる買替差額費相当額を損害として請求することになります。

なお、事故車両の修理をしておらず、また今後修理をする予定もない場合には、保険会社が、修理未了であることを理由に修理費の支払いを拒むことが往々にしてありますが、裁判例では、修理未了であっても既に損害が発生しているとして、修理費相当額の支払いを認めるものがあります。
たとえば、大阪地裁平成10年2月24日判決は、事故車両が現在修理されておらず、また今後も修理する可能性がなかったケースですが、被害車両が現実に損傷を受けている以上、事故による損害は既に発生しているとして、修理費相当額の支払いを認めました。
2.買替差額費
買替差額費と車両の時価
交通事故により、車両が物理的に修理不可能な状態となってしまった場合(物理的全損)、修理費が事故車両の交通事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合(経済的全損)、または車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、その買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合には、修理費ではなく、交通事故直前の車両時価額に買替諸費用を含めた額から、事故車両の下取り価格を差し引いた金額である買替差額費をもって損害額とします。
したがって、交通事故直前の車両の時価を超える修理費を支出していた場合、原則として、時価を超える分の修理費が損害として認められないということになります。このため、車両の時価額が非常に重要になります。
ただし、修理費が事故車両の交通事故直前の時価に、買替諸費用を加えた額を超過している場合でも、修理費がその額が著しく上回っていないとして、修理費相当額を損害として認めた例もあります。
車両時価の算定方法
車両の時価額は、最高裁昭和49年4月15日判決では、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するに要する価格をもって決するものとされています。
この中古車市場での取得価格の算定には、『オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)』や、『中古車価格ガイドブック(通称:イエローブック)』が主に利用されます。ほかには市販の中古車情報誌や、インターネットでの中古車販売価格をもって立証することも可能ですが、この場合は複数の資料を揃えた上で、その平均値を採るようにします。
事故車両と近似する車両が中古車市場に流通していない場合や、車両の年式が相当古い場合等で、中古車市場での取得価格を算定することができない場合には、減価償却の一手法である、定率法を用いて車両の時価を算定することも可能です。
しかし平成19年の税法改正により、平成19年度以降に取得された減価償却資産の償却には、新しい定率法が用いられることになりました。新しい定率法では、車両を1円まで減価償却することができるようになりましたので、減価償却期間を経過した車両の残存価格は1円となってしまい、実勢価格とかけ離れてしまいます。
このような場合には、できる限り年式・性能・走行距離等が近似する車両の市場価格を調査するなどして、事故車両の取得価格を推定できる証拠を収集することが肝要です。
もっともこの点の立証ができない場合でも、残存車検期間に応じた一定の使用価値相当額(裁判例では、登録後14年経過した自動車につき、1日あたり2,000円としたものがあります)を損害として算定する方法もあります。
3.評価損(格落ち損)
評価損とは
事故車両を修理に出したにもかかわらず、機能や外観を修復することができなかった場合、車両に残存する機能的・美観的な欠陥により、車両の市場価値は減少してしまいます。また、事故歴の存在自体によっても市場価値は減少してしまいます。これらの減少した価値を、一般的に評価損などと呼びます。
評価損のうち、機能的・美観的な欠陥が残存することを原因とするものについては、損害として認められることにつき大きな争いはありません。
他方、事故歴の存在を原因とする評価損については、これを認める見解と認めない見解とで分かれている状況です。
裁判例では肯定例が多数ありますが、保険会社との任意交渉で、評価損が支払われることはまずないものと考えておいたほうがよいでしょう。
裁判所では、事故車両の査定額が低下することを、裁判所にとって顕著な事実(=立証不要)であるとは考えておりませんので、評価損を請求する場合には、事故減価額証明書(日本自動車査定協会発行)、自動車修理明細書などを根拠に、現に中古車市場で事故車両の価値が低下していることを積極的に明らかにしていく必要があります。
評価損の算定方法
評価損を算定する際の評価方法については、裁判例上、いくつかの方法が採用されています。
そのなかでも多くの裁判例で用いられているのが、修理費を基準に評価損を算定する方法です。この方法に拠る場合、評価損は修理費のX%相当額として認定されます。
パーセンテージは、基本的には事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷箇所・修理費用の額を総合考慮して算定されています。
評価損として認められる割合としては、20~30%程度が多数を占めますが、これ以上の評価損を認めた裁判例も複数あります。
例えば、東京地裁平成12年3月29日判決は、本件事故が事故車両の新車納品直後に発生したこと、事故車両の新車価格が722万5,000円であるのに対し、修理したと仮定した場合の査定価格が401万6,000円であること、事故車両の受けた衝撃が、その中枢部への影響を危惧される程度のものであったことなどを考慮し、修理費の概ね40%である135万円を評価損として認めました。