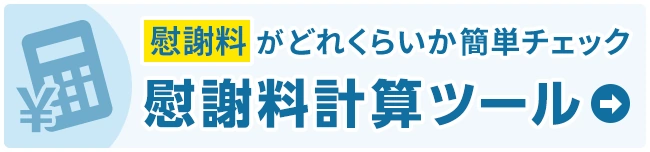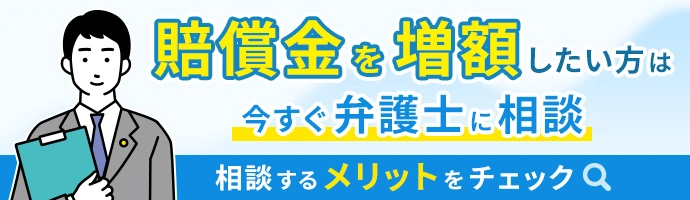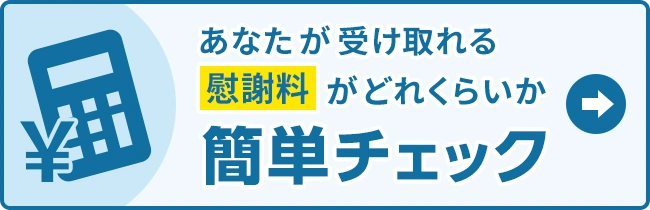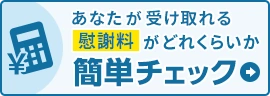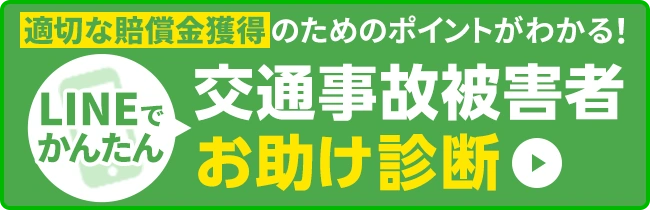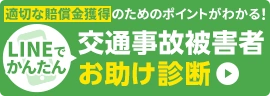交通事故の過失割合でもめるケースとは?もめる理由と解決法も解説

過失割合は、事故の原因となった当事者双方の責任の度合いを示すものです。
交通事故が発生した場合、被害者にも過失(不注意や落ち度)がある場合がほとんどであり、過失割合を巡って当事者間でもめることは珍しくありません。
したがって、適切な過失割合を得るためには、「なぜ過失割合でもめるのか」を知って対応策を検討する必要があるでしょう。
そこで、この記事では、交通事故の過失割合でもめる理由やもめやすいケース、解決法などを解説します。
- この記事でわかること
-
- 交通事故の過失割合でもめる理由
- 交通事故の過失割合でもめるケースと解決法
- 交通事故の過失割合でもめた場合に注意すべきこと
- 目次
交通事故の過失割合でもめる理由
交通事故の過失割合でもめる理由は、大きく分けて下記の2つがあります。
- 当事者双方の話し合いで決めるから
- 示談金額に大きな影響を与える可能性があるから
以下で詳しく解説していきます。
①当事者同士の話合いで決めるから
過失割合は、当事者双方の話合いで決めるのが一般的です。
ただ、被害者と加害者では事故状況に対する認識が違うことが多いものです。そのため、お互いに「相手が悪い」と感情的に対立してしまい、もめてしまう場合があるのです。
②賠償金額に大きな影響を与えるから
被害者に過失があった場合、その過失割合の分だけ賠償金額が減額されます。これを「過失相殺」といいます。たとえば、被害者側の過失割合が20%であれば、損害賠償金は20%減額されてしまいます。
このように、過失割合が賠償金額に与える影響は大きく、特に賠償金が高額になるケースでは、過失割合が1割違うだけで数十万円の差が出ることもあるため、簡単には承諾できないでしょう。
加えて、加害者側の「少しでも支払額を少なくしたい」という思いと、被害者側の「1円でも多く受け取りたい」という思いが対立することから、もめてしまうことが多いのです。
交通事故の過失割合でもめる4つのケースと解決法
交通事故の示談交渉において過失割合でもめることは多いですが、特に問題になりやすいのは下記の4つのケースです。
- 客観的な証拠がないケース
- 損害額が高額であるケース
- 駐車場内で起こった事故や自転車同士の事故であるケース
- 被害者がお年寄りや子どもであるケース
また、それぞれのケースについてご紹介するとともに、その解決法も解説いたします。
①客観的な証拠がない(少ない)ケース
事故の状況を証明する客観的な証拠が残っていない(少ない)場合、事故状況の特定が難しいです。当事者や目撃者の主張する内容に食い違いがあってもどれが正しいのかわからないため、双方の主張が対立しやすくなります。
このようなケースでは、目撃者の証言やドライブレコーダーの映像を収集し、客観的な証拠を確保することが重要です。
②損害額が高額であるケース
高額な損害が発生している場合、過失割合が少し違っただけでも賠償金に大きな影響があるため、もめやすいです。
このようなケースでは、加害者側の保険会社が損害賠償額や過失割合を提示してきたら、過失割合をどのように計算したか、過去の判例をどのように参考にしたかを書面にて回答してもらうことが大切です。
そうはいっても、被害者の方がご自身でそのような対応をするのは難しいでしょう。そのため、交通事故に詳しい弁護士などに相談し、適切な過失割合を判断してもらうといった対応がおすすめです。
③駐車場内で起こった事故や自転車同士の事故であるケース
過失割合は、『別冊判例タイムズ38号』という書籍に記載されている基本割合や過去の裁判例などをもとに検討を行います。
しかし、駐車場内の事故や自転車同士の事故は、参考となる過去の事例が少ないため、もめやすくなります。
このような場合、今回の事故に類似した事故の裁判例を探し、総合的に過失割合を算定することが求められます。
ただし、被害者の方ご自身で対応することは難しいため、交通事故に詳しい弁護士などに相談することをおすすめします。
④被害者が高齢者や子どもであるケース
高齢者や子どもが被害者である事故の場合、証言の信ぴょう性が疑われてしまうことがあります。
このようなケースでは、防犯カメラの映像や事故直後に撮った写真といった客観的な証拠を集めたうえで、適切な過失割合を主張するようにしましょう。
交通事故の過失割合でもめた場合に注意すべきこと
過失割合を巡ってもめる場合には、以下の点に注意することが重要です。
過失割合に関する証拠はできる限り多く提出する
過失割合の判断には、その数値が正当であると示すための客観的な証拠が必要です。証拠が多ければ、その分、正確な判断が下される可能性が高まります。
過失割合を証明するための証拠としては、下記のようなものが挙げられます。
- ドライブレコーダーの映像
- 事故直後の現場写真
- 目撃者証言の収集
- 事故現場の監視カメラの映像
- 実況見分調書、供述調書などの刑事記録
- ケガの診断書
- 車両修理見積書
ただし、被害者の方ご自身だけで過失割合を証明する証拠を集めるのは難しい場合も多いです。
交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、被害者の方に有利な結果を導き出すための証拠を探し、適切な過失割合を加害者側の保険会社に主張していきます。
加害者側の保険会社に過失割合の根拠を説明してもらう
加害者側の保険会社から納得できない過失割合を提示された場合には、その根拠を詳しく説明してもらうようにしましょう。
通常、保険会社は『別冊判例タイムズ38号』という書籍の内容をもとに交渉を行いますので、「どの基準に従ったのか」「その基準から修正した点はあるのか」といった具体的な回答を得られるはずです。
なお、相手から説明された内容を証拠として残しておくため、やり取りは書面またはメールで行いましょう。
過失割合について警察は判断しない
交通事故の過失割合について、警察が判断したり決めたりすることはありません。これまでご説明したとおり、過失割合を決めるのは事故の当事者です。
加害者側の保険会社の担当者に冷静に対応する
加害者側の保険会社の担当者の対応がよくない場合でも、冷静に対応するようにしましょう。感情的になってしまった場合、交渉がこじれる可能性があります。
被害者の方ご自身での対応が難しい場合には、弁護士などに依頼し、代わりに対応してもらうのも一案です。
過失割合でもめて示談できない場合の解決法
過失割合でもめてなかなか示談できないときに有効な主な手段としては、下記の3つが挙げられます。
- ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
- 調停を申し立てる
- 弁護士に相談・依頼する
ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
交通事故の紛争に関するADR(裁判外紛争解決手続)は、中立な立場で仲裁を行い、交通事故の当事者双方の言い分を鑑みた解決策を提案します。
交通事故の紛争解決のために利用できるADR機関で代表的なのは下記の2つです。
- 交通事故紛争処理センター
- 日弁連交通事故相談センター
具体的なADRの紛争解決の流れは、下記のとおりです。
- 弁護士への法律相談
- 和解のあっせん
- 審査手続
弁護士への法律相談
ADRの担当弁護士が法律相談に乗ります。相談者が提出した資料を確認し、問題点を整理したり、アドバイスを行ったりします。
和解のあっせん
相談者が「和解のあっせん」の申立てをした場合は、ADRの相談担当弁護士が当事者双方から話を聞き、争点・賠償額などについての和解案を提案します。
合意できた場合には、相談担当弁護士の立会いのもとで、示談書または免責証書を作成します。
審査手続
和解のあっせんで和解が成立する見込みがない場合に、審査手続に移行します。
審査員が争点や事故の内容について当事者双方の主張を聴き、結論を示す裁定が行われます。
被害者側が裁定に同意すれば示談が成立しますが、納得できない場合はADRでの手続は終了し、裁判などに移行します。
調停を申し立てる
調停を申し立てることにより、調停委員と呼ばれる中立的な第三者が、当事者双方の言い分を公平に聴取・調整して、合意を目指すことができます。
調停委員は、双方に対して相手方の主張を伝えたり、説得にあたったりします。最終的には、当事者双方の主張を踏まえて裁判官が解決案を作成し、両当事者に提示します。
この解決案に双方が合意できれば、調停が成立となります。
弁護士に相談・依頼する
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、適切な過失割合を得るための資料集めはもちろんのこと、加害者側の保険会社との交渉も代行してもらうことができます。
上記以外の解決方法について知りたい方は下記のコラムをご覧ください。
まとめ
交通事故の過失割合は、賠償金額に影響するため示談交渉のなかでももめやすいポイントです。主張が食い違う加害者側との示談交渉を、被害者の方ご自身で行うのは荷が重いことでしょう。
弁護士であれば、過去の判例を参照のうえ適切な過失割合を算定し、加害者側に主張することが可能です。
ぜひ、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な対応についてアドバイスを受けることをおすすめします。
交通事故の被害はアディーレにご相談ください
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。
また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用
加害者側と過失割合でもめており、対応にお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。